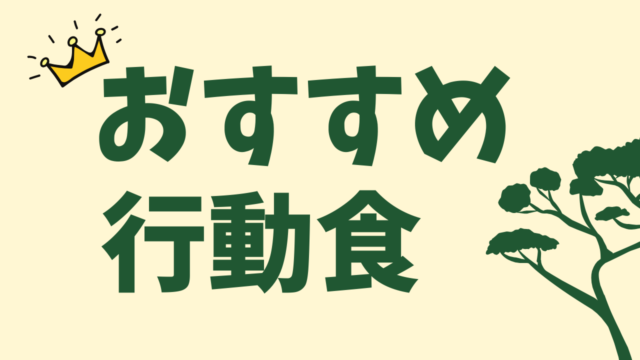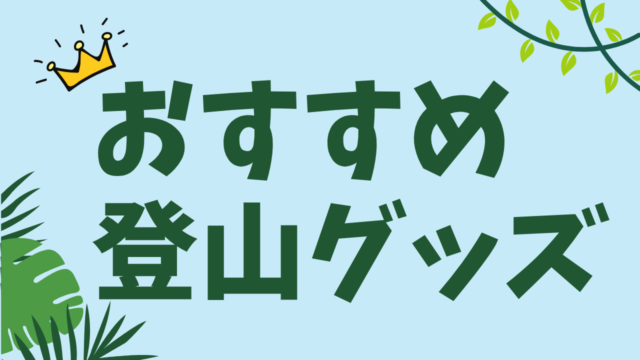「山でトイレってどうすればいいんだろう?」
「汚いって聞くけど…」
といった不安を抱えていませんか?
実は、山でのトイレは街中とは大きく異なり、特別な知識と準備が必要です。
本記事では、登山初心者のしゅうママが、初心者目線でリサーチした山のトイレ事情を解説していきます。
・快適な山行のための具体的な対策と持ち物
特に女性にとっては、男性に比べて手間や時間がかかるため、事前にしっかり備えておくことが、快適で安全な山行のために非常に大切になります。
バッチリ対策をすれば不安がなくなり、快適な山行になること間違いなしです。
【山のトイレ事情】なぜ山のトイレは大変なの?
山でのトイレがなぜ難しいのか、その理由を理解することが第一歩です。
設備の不足と維持の困難さ
街中とは異なり、山地ではトイレの設置や維持がとても難しいんだ。
資材の運搬、建設、そして汚物の処理には多大な労力、水、エネルギーが必要です。
このため、多くの山ではトイレ自体が少なかったり、あったとしても混雑していたり、故障で使用できなかったりする場合があります。
環境への配慮が必須
山は本来、動物や植物の生活の場であり、登山者は「侵入者」であるという自覚が必要です。人間が生きていく上で避けて通れない「排泄」は、入山者が少なかった時代には許されたことも、現在では許されない行為となっています。
女性特有のデリケートな問題
生理など、女性ならではの体調変化は登山中にも起こり得ます。
生理中はデリケートゾーンの不快感や漏れの心配、ナプキン交換の難しさ、そして使用済み生理用品の持ち帰りといった、男性にはない悩みが生じます。
また、冷えは腹痛などの生理痛を悪化させる可能性もあります。
【山のトイレ事情】具体的な対策と持ち物
安心して登山を楽しむためには、事前の準備と適切な行動が不可欠です。
- 登山前の準備
- 登山中の持ち物とマナー
- 野外で排泄せざるを得ない場合(最終手段)
- 生理対策
① 登山前の準備
② 登山中の持ち物とマナー
地図に記載されているトイレが使えない場合や、緊急時に備えて、携帯トイレは必ず持参しましょう。
近年では、環境省や地方自治体の支援、山小屋経営者の努力により、山のトイレも整備が進んできていますが、それでも問題の根本は登山者自身のマナーと協力にあるとされています。
小のみの筒状タイプ
コンパクトで凝固剤が最初から入っているもの
大小兼用の手持ちタイプ
両手で支えることで安定して使える大きめの袋タイプ
地面に広げるタイプ
ビニール袋を地面に広げて使用し、後から凝固剤を振りかける、または凝固シートが付属しているタイプ
携行性、価格、使いやすさ、防臭力、袋の強度、付属品の豊富さなどを考慮して選びましょう。特に防臭力は重要です。
消臭袋を別に用意しておくと安心です。ペット用や赤ちゃん用なども代用できます。
ペット用ウンチ処理袋
赤ちゃん用おむつの消臭袋
使用済み紙は必ず持ち帰る
排泄物はもちろん、使用済みの紙はすべて自宅まで持ち帰りましょう。密閉型のビニール袋を必ず携行し、汚れた面を内側にしてファスナー付きの袋に入れれば、臭いや汚れはほとんど気になりません。ティッシュペーパーは水に流せるタイプが必須です。
トイレットペーパーをジップロックなどに入れておくのも手です。
③ 野外で排泄せざるを得ない場合(最終手段)
場所の選定
沢や水辺から最低でも20〜30mは離れ、水場の上流は絶対に避けよう。
植物が生い茂り、落ち葉があり、雨で流される心配のない地点を選び、砂礫地や岩場は避けましょう。

後始末
スコップを持参し、汚物が隠れる程度の穴を掘って土をかけ、完全に埋没処理をしてください。雪上でも雪穴を掘って埋めましょう。
プライバシーの確保
ポンチョや簡易テント(ツェルト)を活用すると、周囲の視線を遮ることができるよ。折り畳み傘でもOK。
ただし、登山道から離れすぎると道に迷ったり、滑落の危険があるため、周囲に十分注意して行動しましょう。
④ 生理対策
生理用品の工夫
登山中のズレや擦れを防ぐために、タンポンや吸収型サニタリーショーツ、スポーツ用ナプキンを賢く取り入れましょう。
これにより、ナプキン交換の頻度を減らし、使用済みナプキンの量も減らせます。
衛生用品
山のトイレにはウォシュレットがないため、デリケートゾーンを清潔に保つために、ノンアルコールのウェットティッシュや赤ちゃん用のおしり拭きを携行しましょう。使い切りビデ(クリーンシャワー)も有用です。
持ち帰り方
使用済みの生理用品は、匂い漏れを防ぐために密閉性の高いジップロックなどに入れて持ち帰りましょう。
冷え対策
腹部を温めるために、腹巻や使い捨てカイロ、温熱シートを活用しましょう。身体が冷えると腹痛などが悪化する可能性があります。
同行者との共有
恥ずかしいかもしれませんが、もしもの時のために、生理中であることや体調が思わしくないことを同行者に伝えておくと、理解とサポートが得られやすくなります。
無理はしない
体調が優れないときは、無理せず登山を中止したり、工程の短い山やトイレが整備された山に変更したりするなど、リスケジュールも大切な選択肢です。
自分の体を最優先に考えよう。
まとめ
山でのトイレ問題は、登山者一人ひとりのマナーと積極的な協力が最も大切であり、欠かせません。
- 登山前の準備
- 登山中の持ち物とマナー
- 野外で排泄せざるを得ない場合(最終手段)
- 生理対策
事前の計画をしっかり立て、携帯トイレや持ち帰り用の袋など必要なものを持参し、自然への負荷をかけない行動を心がけることで、皆が気持ちよく、楽しい山旅をいつまでも続けられることに繋がります。
しっかり準備して、まずはトイレのチェックから始めましょう。