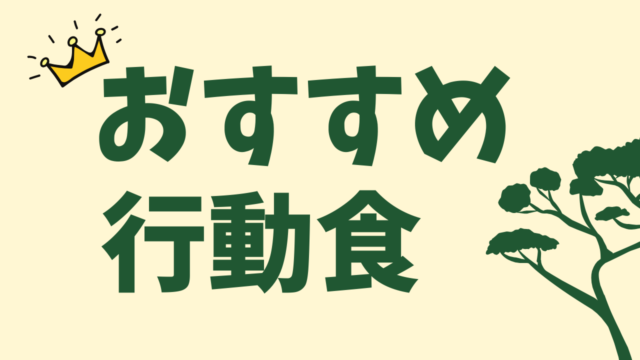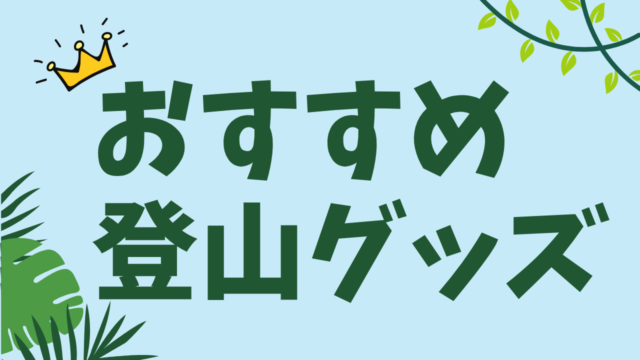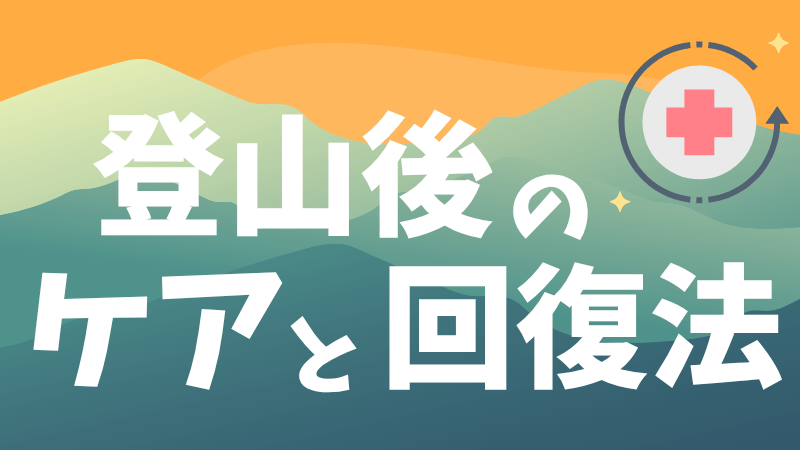「登山の翌日、階段が地獄…」
「もう登りたくない…」
そんな経験ありませんか?
特に普段あまり運動をしていない女性だと、帰宅してから「足がガクガクで動けない…」と感じることも少なくありません。
この記事では、なぜ筋肉痛になるのか、登山後の効果的なケアの仕方、回復を早める栄養のポイントまで分かりやすく紹介します。
下山後にちょっとしたケアをするだけで、つらい筋肉痛やだるさをぐっと減らせます。体をしっかりいたわれば、次の登山も楽しみにできるはずです。
もう「筋肉痛が怖いから登山はちょっと…」なんて思わずに、もっと気軽に山歩きを楽しみましょう!
「筋肉痛つらい…」なぜ登山で筋肉痛になるの?
筋肉痛の原因は100%特定されているわけではありませんが、一般的には、運動によって筋肉が傷つき、それを修復する際に起こる炎症の痛みだと言われています。
- 登山中の筋肉使用:特に太もも、ふくらはぎ、お尻の筋肉を集中的に使用
- 筋繊維の微細な損傷:普段の運動では経験しない強い負荷により筋肉繊維が傷つく
- 炎症反応:傷ついた筋肉を修復するため、体が炎症反応を起こす
- 痛みの発生:この炎症反応が筋肉痛として感じられる
登山では、特に下り坂での「伸長性収縮(エキセントリック収縮)」と呼ばれる、筋肉が伸びながら力を発揮する動きが組織の損傷を引き起こしやすく、筋肉痛の原因となりやすいのです。
- 長時間の登り:ふくらはぎや太ももの裏側
- 急な下山道:太ももの前側
- 重いリュックを背負った登山:背中や肩
- 不整地の歩行:足首周辺の小さな筋肉
筋肉痛が運動直後ではなく、翌日以降に遅れて現れるのは、損傷した筋肉に白血球などが集まり、炎症反応が起こることで生成される物質が筋肉を包む膜を刺激し、それが痛みとして認識されるまでに時間がかかるためです。
日頃から運動する習慣がないと、血液の巡りが弱いため、修復成分が集まるのに時間がかかり、筋肉痛が遅れて出ると感じることもあるよ。
登山後の体のケアと回復方法
筋肉痛を和らげ、疲労を早く回復させるためには、主に次の3つのアプローチが重要です。
- 休養
- 栄養
- ケア
1. しっかり休む「休養」
十分な睡眠の確保
リカバリーの基本は「寝ること」です。
筋肉の疲れと損傷を回復させるためには、7時間以上の十分な睡眠を心がけましょう。
私たちの体はノンレム睡眠中に筋肉の緊張が緩み、疲労回復が促されると言われています。
就寝直前の食事やスマホ・パソコンの使用を避け、朝に太陽の光を浴びるなど、睡眠の質を高める工夫も大切です。
2. 回復を助ける「栄養」
登山で酷使された筋肉の回復には、材料となる栄養素の補給が不可欠です。
糖質とたんぱく質を素早く補給
下山後は、体内のエネルギーが不足し、筋肉が分解されている状態です。そのため、できるだけ早く糖質とたんぱく質を摂取することが重要です。
コンビニで手軽に買えるおすすめ食品
移動中や疲れている時でも手軽に摂れるものとして、以下の食品が挙げられます。
サプリメントの活用
食事から十分な栄養が摂りにくい場合や、効率よく補給したい場合はサプリメントが便利です。
25km走の3日前からBCAA含有飲料を摂取した陸上選手でLDHの上昇が有意に低かったという研究結果や、3日間の集中トレーニング中にBCAA含有飲料を摂取した選手で筋肉痛や疲労感が抑制されたという研究結果があります。
登山中のコンディショニングにも役立つと考えられています。
特に、持続力維持と疲労回復に有効なビタミンB群を含むプロテインの摂取もおすすめです。
3. 体をいたわる「ケア」
下山後のお風呂とアイシング
下山後の入浴は気持ち良いですが、入り方で疲労回復効果が変わります。
**患部に熱や痛みがある場合は、まず冷やす(アイシング)**ことが大切です。アイシングは炎症を抑え、痛みを和らげ、疲労の拡大を防ぐ効果が期待できます。氷のうなどで10〜15分程度を目安に行いましょう。水風呂や冷水シャワーも効果的です。
アイシングを終えた後や、熱や痛みがなければ、ゆっくり温めて血流を促進させましょう。ぬるめのお湯や温泉に浸かることで、損傷した筋肉の回復に必要な酸素や栄養が運ばれやすくなります。運動後すぐではなく、30分ほど横になってから入浴するのがおすすめです。
ストレッチと筋膜リリース
具体的なストレッチとして、太もも前側、お尻、太もも付け根、足裏のマッサージなどが挙げられます。
「筋肉痛つらい…」普段からの予防も大切
筋肉痛になりにくい体を作るためには、普段から以下のことを意識してみましょう。
日頃からの運動習慣
登山は持久力に加えて筋力も必要な運動です。普段から運動不足の人が急に登山をするのは避けましょう。
毎週登山ができなくても、スクワットや体幹トレーニングなどで下半身を鍛えることを習慣にすると良いでしょう。
週に2回程度、48時間以上の回復期間を設けながらトレーニングを行うのがおすすめです。
登山用タイツの着用
着圧で疲労を軽減する「コンプレッション系タイツ」や、筋肉・関節の動きをサポートする「サポート系タイツ」、その両方を兼ね備えた「ハイブリッド系タイツ」があります。
自分に合ったタイツを選ぶことで、登山中のパフォーマンス向上や、登山後の疲労・筋肉痛の軽減に繋がります。
リカバリーを助けるアイテム
まとめ:適切なケアで次の登山も快適に!
登山後のつらい筋肉痛や疲労感は、適切な「休養」「栄養」「ケア」を行うことで大きく軽減できます。
下山直後からのアイシングや、糖質・たんぱく質を中心とした栄養補給、そして回復を助けるアイテムの活用、さらには普段からの運動習慣が、あなたの登山ライフをより快適で楽しいものにしてくれるでしょう。
これらのケアを取り入れて、次の登山も思い切り楽しみましょう!